|
PCV
| |
- ブローバイ、ブローバイ・ガス
ピストンリングからクランクケースに吹き抜ける混合気の未燃焼ガス
燃え残りの煤と気化した燃料が含まれるので、煤によるエンジンオイルの汚れ、燃料によるエンジンオイルの希釈、劣化を起こし、結果的には、シリンダーやピストンの摩耗を促進させる
- クランクケース内圧の設計値
ウェットサンプ :-0.005kg/cm^2 以下の「負圧」
ドライサンプ :-0.1kg/cm^2 程度の「負圧」
- クランク・ケースの負圧とキャビテーション
・クランクケースの負圧が低い場合
キャビテーション(気泡が発生すること)が発生しやすくなり、極端な場合には、
オイルポンプがエア噛みを起こして、オイルがエンジン各部に圧送されません
(滅多に起こることではありません)
・クランクケースの負圧が高い場合
通常、オイルの戻りは重力、負圧に頼っています。オイルの戻りが悪くなります
注意:負圧の度合の違いによる問題です。
- エンジンの歴史とブローバイガス還元
密閉型、オープンタイプ、シールドタイプ、クローズドタイプ
- 密閉型 1900年〜 内燃機関登場時から
第一次世界大戦後〜第2次世界大戦前のエンジンあたりです
クランク室は密閉でブローバイガスの還元はありません
クランク室の圧力は正圧(大気圧以上)になる場合もありました
オイルシール、オイル注入口はこの高い圧力に対応できる形式になっており、
注入口のフタはネジで締め付ける形式となっています
この世代のエンジンでは、GearBoxはグリス封入の形式のものもあります
- オープンタイプ(大気開放) 1930年
クランクケースにブリーザーが設置され、ホースで大気開放されていました。
なお、4輪の場合にはブリーザーホースはヘッドに設置されているのが一般的です
中間にオイルキャッチタンクをつけている場合もあります。吸気ダクト、あるいは、エアクリーナケースには接続されていないので、吸入負圧で、クランクケース内の圧力を下げることはできない
。
ブローバイは大気中に捨てられる 現在では車検は通らない(?)

- シールドタイプ(エアクリーナケースに還流) 1960年
ヘッド、あるいは、グランク室からエアクリーナーBox、あるいは、吸気ダクト(サクションパイプ
、吸気ダクト、インテークパイプ))戻している。但し、ワンウェイ・バルブなどは無い
ブローバイは吸気に混ぜられて、再び燃焼室に送られる
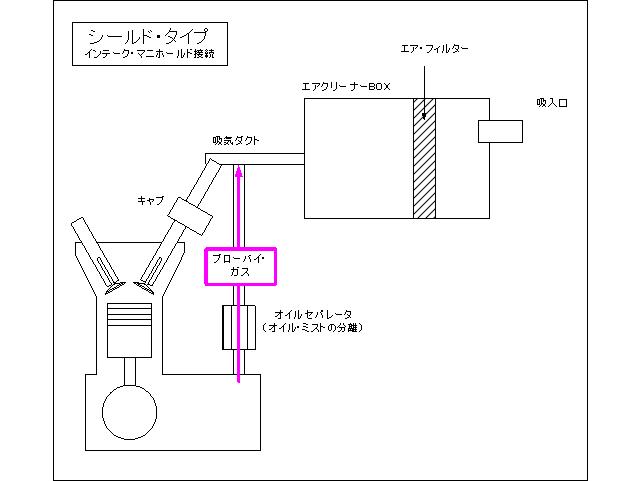
オイルセパレーターが設置されていない車種も有ります
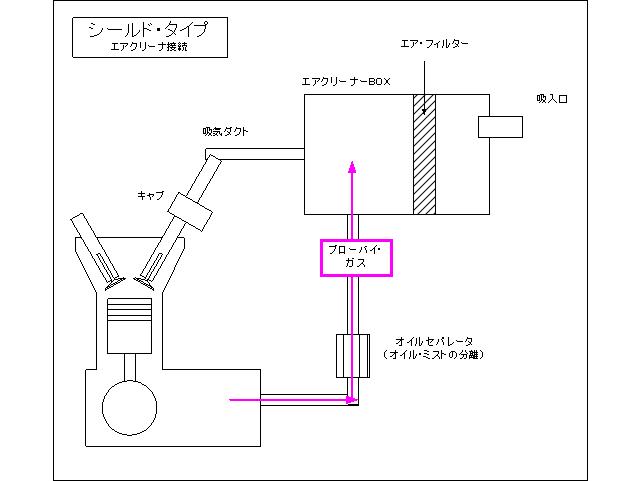
オイルセパレーターが設置されていない車種も有ります
- R100/R80・モノサス、R100R/R100GS シールド・タイプ(吸気ダクト接続)
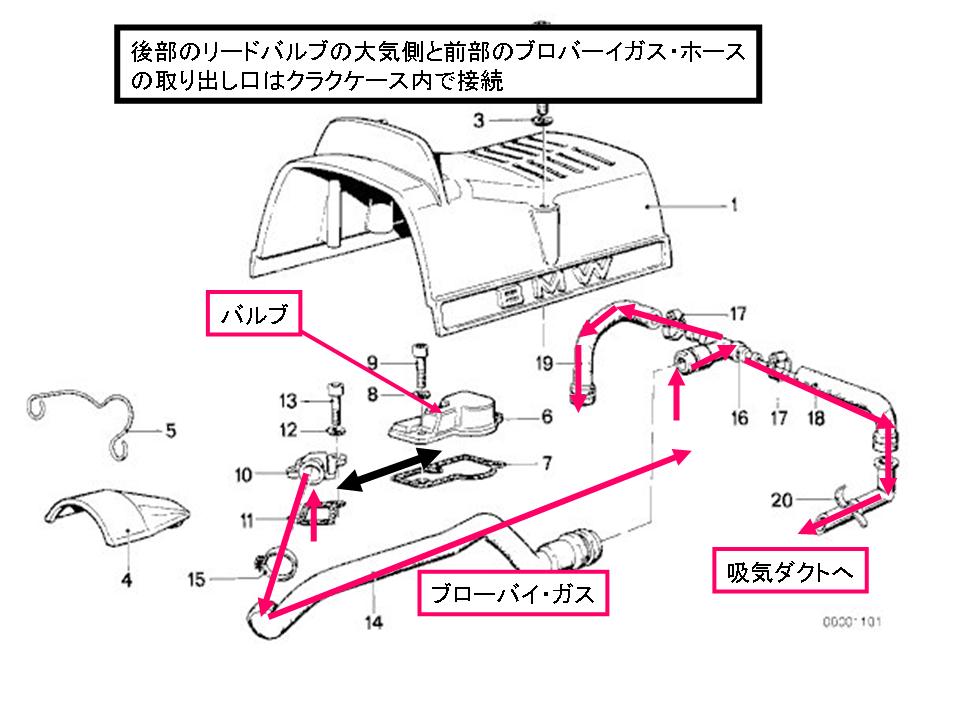
エンジン前部のブリード・ホース取り出し口・直下には「棚状」のオイルセパレータが設置されています。
エンジン後部のリードバルブ(reed-valve:PCVと同じくワンウェイ・バルブ)
の「出口側」は極、小径の穴でクランクケースに戻される構造です。
/5など古いモデルでは、エンジン前部のブリードは無く、後部のリードバルブの出口はエアクリーナー・シュラウドに戻されていました。(吸気ダクトでは無く、エアクリーナー・シュラウドです。)
エンジン後部のリードバルブの動作は未調査
2V-Boxerのクラクケース内圧の変化は2気筒では最も大きく、1,000cc単気筒と同じです。また、2系統+PCVバルブを使っている世代でもありません。 このリードバルブがどの様な動作をしているのかは不明です。
http://bmwmotorcycletech.info/oilsketch.htm
Snowbum氏のHPでも色々説明されていいますが、良くわかりません。
参考:油圧は、1bar〜5barで制御されています。(油圧が5bar以上になった場合には、オイルフィルターのバイパス・バルブ、タイミングケース内のブリザー・バルブ:クランクシャフト・前部・メインベアリングの後:で減圧されます)
- 排気バルブに導く方法、SACS、2次エア装置 Pulse-Air・システム
初期のカリフォルニアの排ガス規制対策
ブローバイを「新しい空気]と一緒に排気バルブ側に導入して燃焼させるもの、エンブレ時には盛大なアフターファイヤが出る。 (エキゾーストが完全に接続されていない状態と同じ)
アクセル・。オフでは、エンジン・クランク室〜エアクリーナーBOX〜排気ポートと導かれている経路で、アクセルオフでは、キャブ側の負圧が無くなり、大量の新規エアが排気ポートに供給される為です。
- クローズドタイプ(PCVバルブを使用)
現在の4輪、2輪のほとんど全て
2系統のチューブがある
オイルセパレータはPCVバルブ系統だけに搭載されてい4輪が多い
(メイン・ブリーザ・ホースにはオイル・ミストが少ないから)
注意:1960年以降の4輪、 2輪の場合には、その後長く、シールド・タイプだった
ヘッド、あるいは、クランク室 --- PCV ------------------ 吸気ダクト
ヘッド、あるいは、クランク室 ---(バルブ類無し)--- エアクリーナー
エンブレ時、アイドリング時には、インテークマニホールドの負圧によって、PCVバルブ〜吸気ダクト系統からブローバイ・ガスをブリードし、バルブ類無しの系統からはエアクリーナーから、新鮮な空気がクランク・ケースに供給されます。
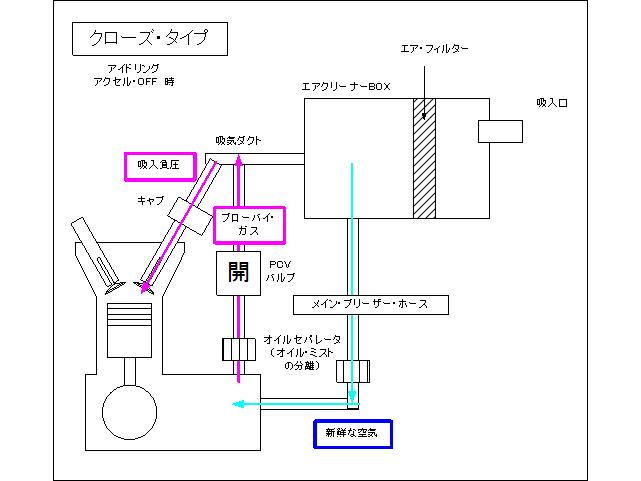
高回転時、一定回転時には、PCVバルブ系統は閉じて、バルブ類無しの系統からエアクリーナーにブリードされます。
これは、ブローバイ・ガスの発生はアイドリング時に多い為です。

注意:説明図では、取り出し口はクランクケースですが、現在は2系統ともに、ヘッドからの取り出しが一般的です。 ヘッドからの取り出しの場合には、棚状のオイル・セパレータがヘッドカバーのブリーザー・ホース取り出し口の下にあります。 OHC/DOHCでカムチェーン駆動の場合には、チェーン部の開口部が大きくクランクケースとエンジンヘッドの圧力差はありませんが、コグトベルト駆動(エンジン外部)の場合には、クランクとエンジンヘッドの連結穴を確保する必要があります
|